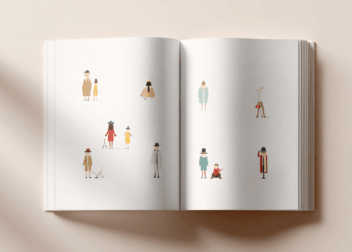ECサイトブログの効果的な活用法:集客とSEOの両立
現代のEC市場は競争が激化しており、ネットショップの運営者は常に売上向上と集客のための新たな手段を模索しています。なかでも「ブログを活用したコンテンツマーケティング」は、比較的低コストかつ中長期的に効果を期待できる強力な施策として注目度が高まっています。本記事では、ECサイト内のブログを活用して集客力を強化しながら、SEOによる検索流入・ブランド認知・購買促進を同時に実現するための考え方と手法を詳しく解説します。自社サイトのブログ運営をこれから始める方や、すでにブログを運営しているものの効果を出しきれていない方にとって、実践的なヒントとなる情報をまとめています。ぜひ参考にしてみてください。
Contents
ECサイトブログがもたらすメリット
ECサイトにブログを設置する最大のメリットは、“自社発信の有益なコンテンツ”を通じてユーザーと接点を持ち、最終的には商品購入につなげられる点です。商品ページだけでは伝えきれない情報を提供し、ブランドへの興味関心を高めたり、検索エンジンから新規ユーザーを集客したりと、多面的なメリットが期待できます。ここでは大きく3つの観点から、ECサイトにおけるブログ運用の意義を見ていきましょう。
ブログがSEOに寄与する
商品ページはどうしても「商品名+型番」や「価格・スペック」といった限定的な内容になりがちです。一方、ブログ記事では商品の使用例やハウツー、背景ストーリーや専門知識を詳しく紹介できるため、ユーザーが検索しそうな多様なキーワードを狙いやすくなります。いわゆるロングテールキーワード(「○○の使い方」「○○の選び方」「○○のコーデ事例」など)にも対応しやすく、それらが検索結果で上位表示されると、継続的にトラフィックを生み出してくれる“集客資産”となるわけです。
また、ブログを同一ドメイン内で運営することで、ドメイン全体の評価が高まるといわれています。商品ページだけだとコンテンツ量が乏しくSEO的に不利なケースでも、ブログ記事を蓄積することでサイト全体が「情報量豊富で役立つサイト」と認識され、検索エンジンからの評価向上につながります。長期的には広告費に頼らない「オーガニック流入」が安定するため、費用対効果の面でも魅力的です。
ブランド認知とユーザーとの接点強化
ネットショップでは実店舗と違い、顧客と直接コミュニケーションが取りにくい側面があります。しかしブログを活用すれば、商品の開発秘話やスタッフの思い、使用シーンの提案など、文字通り「ストーリー」を発信できます。こうしたバックグラウンドを知ると、ユーザーは「このショップにはこだわりがある」「信頼できそう」という好感を抱きやすくなり、ブランド認知・理解が深まります。
特にInstagramやYouTubeなど外部SNSと連動させると、記事を読んだユーザーがSNSアカウントをフォローし、継続的に接点を持ってくれる可能性が高まります。さらにブログ記事からメールマガジンの登録フォームへ誘導すれば、定期的にセール情報や新商品を告知できるようになり、購買チャンスの最大化を図れます。このようにブログは単なる文章の集合以上に、ブランドコミュニケーションの中核として機能し得るのです。
コンテンツマーケティングによる持続的な成果
経済産業省の調査によれば、ここ数年の国内EC市場は着実に拡大を続けており、競合も増えているのが実情です。広告費をかけた即時集客も大切ですが、広告は費用をかけ続けなければ効果は継続しません。一方で、コンテンツマーケティングの最大の特徴は“資産”になることです。良質なブログ記事をストックしていけば、その内容が評価される限り、長期間にわたり検索エンジンからアクセスを呼び込み、ブランド認知や売上に寄与し続けます。
さらに、記事をきっかけに雑誌や他Webメディアなどから取材や転載オファーを受けることもありえます。そうなれば無料で大きな露出を得られ、結果的に広告費以上のメリットをもたらす可能性もあります。つまり、ブログを通じて地道にコンテンツを育てる行為は、**長期的な視点での“攻めの集客”**とも言えるのです。
有効なコンテンツ企画と運用方法
ECサイトのブログにおいては、コンテンツをいかに継続的に生み出し、読者にとって役立つ情報を提供し続けられるかが重要となります。ここでは具体的なコンテンツの企画から、運用を成功させるポイントまでを詳しく解説します。
商品に関連する有益なコンテンツの例
- ハウツー記事: 「使用方法」「お手入れの仕方」「最適な組み合わせ方」などを解説する記事は、購入前のユーザーだけでなく、購入後のユーザーもターゲットにできます。たとえばスキンケア用品なら「乾燥肌向けの正しいスキンケア手順」、キッチン用品なら「上手なメンテナンス方法」「料理が楽しくなる時短テクニック」など。実際の利用シーンや具体的な手順を示すことで、購買意欲と製品への信頼感が高まります。
- レビュー・ランキング記事: 「10代向けの人気アイテムトップ5」「この冬買うべきアウター厳選5点」など、比較や順位付けをするコンテンツは購買前の情報収集で多く検索されます。自社製品のみならず競合商品とも公正に比較してみる、あるいはユーザーから寄せられた口コミをまとめるなど、読者視点の公平感を大切にすると一層信頼度が上がります。
- 季節のトレンド・特集記事: 春夏秋冬、あるいはイベントシーズンに合わせた特集は、記事のネタにしやすい上、ユーザーの検索ニーズとも合致しやすいです。ファッション系であれば「夏のワンピース特集」「秋のカーディガンコーデ術」、フード・キッチン系なら「お正月料理特集」「アウトドアで楽しむ秋キャンプレシピ」など、季節感を押し出すことで魅力的な記事ができます。
- 顧客レビューや使用レポート: 実際に利用した顧客やスタッフによる生々しい感想は、多くのユーザーにとって「買う前に知りたい情報」です。例えばアパレルならスタッフが実際に着用してみて写真を掲載し、「身長別サイズ感レポート」を書くと非常に参考になります。ECは実物を試せないデメリットがあるため、こうした“リアルな声”は消費者の不安を和らげる強い武器になります。
- 商品開発や企業ストーリー: 自社がどのような思いで商品を作っているか、あるいはどのような過程を経て誕生したのかといった背景を知ると、ユーザーは製品そのものに愛着や共感を抱きやすくなります。これは特にクラフト系商品やオーガニック食品など、“こだわり”や“ストーリー”が重要なジャンルで効果が大きいでしょう。
ユーザーの検索意図を捉えるキーワードリサーチ
ブログ記事を書く前には、必ずキーワードリサーチを行うことが大切です。たとえば「洗濯機 おすすめ」「筋トレ 初心者 器具 必要」など、検索されやすい複合キーワードを見極め、それを自然に盛り込んだ記事を作ることで、特定のニーズを持つユーザーを効率よく集客できます。
- サジェスト機能: GoogleやYahoo!の検索ボックスにキーワードを打ち込むと表示される補完候補が、ユーザーが実際に検索しているワードをリサーチする手がかりになります。「EC ブログ 運用」「EC ブログ 効果」などの組み合わせもサジェストで見つかることがあるので、そこから記事テーマを探すのも一手です。
- キーワードツール: GoogleキーワードプランナーやUbersuggest、他にも国産のSEO支援ツール(ミエルカ、Keywordmapなど)を使えば、月間検索ボリュームや競合性、関連語を体系的に把握できます。競合他社が注力していないニッチなキーワードを見つけ出すロングテール戦略が、ECサイトのブログには効果的です。
- 検索意図の分析: たとえ同じキーワードでも、ユーザーが「購入を前向きに考えている」のか、「情報収集段階なのか」、または「問題解決を探しているのか」など意図はさまざまです。上位表示されている競合サイトの内容を参考に、「ユーザーはどんな回答を求めているのか?」を想定し、必要な情報を網羅した記事を作ることが重要となります。
タイトル設計と記事構成の工夫
検索結果でまず目に留まるのはタイトルとメタディスクリプションです。タイトルはSEO・クリック率(CTR)両面で大きく影響するため、以下のようなポイントを押さえましょう。
- キーワードを盛り込む: 「○○ おすすめ」や「○○ 比較」のように、狙いたいキーワードを含めて記事の内容を的確に示します。
- 数値・具体性: 「〇〇選」「△△ガイド」「初心者向け3ステップ」など、数字を使うと具体性が増してクリックを促しやすくなります。
- 文字数制限に注意: タイトルが長すぎると検索結果に途中までしか表示されないため、全角30文字前後に収めると良いでしょう。
記事の構成としては、大きな見出し(H2)・小見出し(H3)などで情報を整理し、読み進めやすい流れを作ります。冒頭(リード文)で記事の結論や要旨を簡潔に提示し、中盤で根拠や具体例を詳しく述べ、最後にまとめやCTAを配置するのが定番パターンです。
投稿頻度と長期的運用
ブログを月に1度も更新していないサイトは、「更新が止まっている」と見なされ、読者から興味を失われるばかりか、検索エンジン的にもマイナス要素があるといわれています。理想としては週1本以上、可能であれば週2~3本程度を安定して公開できるとSEO効果が高まりやすいです。
もちろん、無理に毎日更新して品質が下がるのは本末転倒です。継続可能な頻度で、かつ質を重視したコンテンツを積み重ねることが大切になります。小規模運営なら月1~2回でも良質な記事を書くほうが、低品質記事の大量投下よりも遥かに有意義です。また、古い記事のリライト(情報の更新やタイトルの再工夫)も大切で、とくに1年以上経過した記事はSEO視点でも情報鮮度の面でもアップデートを検討してください。
SEO観点での最適化ポイント
集客とSEO効果を同時に狙うには、やみくもに記事を投稿するのではなく、検索エンジンが高く評価する“最適化”を意識する必要があります。ここでは具体的にどのようなSEO施策を行えばよいのかを解説します。
適切なキーワード配置
前項で述べたキーワードリサーチで抽出した言葉を、記事のタイトル、見出し(H2, H3)、本文、メタディスクリプションなどに適度に配置しましょう。過度に詰め込む(keyword stuffing)のは逆効果ですが、自然な流れで複合キーワードや関連用語を散りばめると、検索エンジンにテーマの網羅性をアピールできます。
特にタイトルタグへのキーワードの含有は大切です。検索結果一覧で表示されるため、読み手が「このページは私の求める情報がありそうだ」と判断できるかどうかを左右する重要な要素になります。また、最初の見出し(H2)や本文冒頭にキーワードを入れると、検索エンジンに「このページは○○について書かれている」と明確に示す効果があります。
内部リンク戦略
同じサイト内で関連性の高いページや記事を相互にリンクさせることは、ユーザーの回遊性を高めるだけでなくSEO評価向上にも貢献します。たとえば「この商品の詳しい比較は別記事で解説しています」とリンクを張ると、クローラーがサイト内を巡回しやすくなるだけでなく、ユーザーも欲しい情報へスムーズにアクセスできます。
- アンカーテキスト: 「詳しくはこちら」「クリック」など抽象的な文言ではなく、「○○の選び方を詳しく解説した記事」など具体的なテキストにするとユーザーにも検索エンジンにもわかりやすいです。
- 階層やカテゴリの整備: カテゴリ分けやパンくずリストを整え、「blog/カテゴリ名/記事タイトル」のようにURL構造をわかりやすく保つとSEO上のメリットがあります。
商品ページへの導線(リンク)も重要です。特にブログ記事を読んで興味を持ったユーザーがすぐ商品ページに移動できるように、複数箇所にリンクを設置すると購買率も向上しやすくなります。
構造化データの導入
検索エンジンはサイト内の構造やコンテンツ内容をより正確に理解するため、Schema.orgのArticleスキーマなどを用いた構造化データのマークアップを推奨しています。適切に実装すれば、検索結果に記事の著者名や評点、レシピ情報などがリッチリザルトとして表示される場合があり、クリック率(CTR)の向上が期待できます。
一方、構造化データそのものが直接ランキングを左右するわけではありません。しかし間接的には「検索結果で目立つ→クリックされやすい→結果的に順位も上がりやすい」という好循環を生む可能性があります。WordPressを利用している場合はプラグインなどで簡単に実装できるケースが多いので、機会があれば取り入れてみましょう。
サイト速度とモバイル最適化
Googleはページの表示速度がユーザー体験(UX)に大きく影響するとして、ページスピードをランキング要因の一つに挙げています。画像ファイルの最適化やキャッシュ活用、不要なスクリプト削除などでできるだけ表示を高速化しましょう。モバイル端末での読み込み速度も重視されるため、レスポンシブデザインを確保し、スマホ閲覧時に余計なエフェクトや画像が遅延しないよう工夫が必要です。
ECサイトにおいて、ユーザーが商品ページへ移動して購入を完了するまでのプロセスをスムーズにすることは売上に直結します。たとえブログ記事自体が充実していても、サイト速度が遅く離脱率が高ければ機会損失につながります。テクニカルな部分も含め、定期的にサイトの動作チェックを行うことが大切です。
集客施策と購買促進を両立する方法
ブログは“商品を買ってもらうための通過点”であると同時に、“読者の疑問や興味を満たすための有益コンテンツ”でもあります。この両立を図るためには、記事の中で売り込みすぎることなく自然に購買へ誘導する仕掛けを取り入れることがポイントになります。
効果的なCTA(Call To Action)の設置
CTAとは「具体的な行動をうながすための誘導文言やボタン」のことです。記事の本文を読み終えたユーザーが次に何をすればいいのか迷わないように、自然なフローでアクションを提案する仕掛けを作りましょう。たとえば:
- 記事末尾: 「この記事で紹介した商品はこちらから購入できます」「詳しくは商品詳細ページをチェック」というボタンを配置すると、読み終えて興味を持ったユーザーをスムーズに誘導できます。
- 本文中: 例えば化粧品を紹介する記事で「実際の使用感はこちらの商品ページで詳しく確認できます」のようにテキストリンクを挿入すると、“今知りたい”と思ったタイミングで購入ページへアクセスしてもらえます。
- ページ冒頭: 再訪ユーザーや購入意欲の高い人は記事を全部読まずにすぐ商品ページへ行きたい場合もあります。リード文下にさりげなくCTAを配置するのも一つの手です。
CTAの文言は「こちら」「詳しくはこちら」だけではなく、**「〇〇を購入する」「今すぐチェック」「期間限定セールを見てみる」**など、具体的行動とベネフィットを示すとクリック率が向上します。また、ボタンの色やデザインを工夫して、背景や文字色とのコントラストを強くすると目立ちやすくなるでしょう。
ユーザー体験を損なわないデザイン・UX
購買へ誘導する仕組みは大切ですが、ポップアップ広告や強制的なバナーが目立ちすぎると、ユーザー体験が損なわれて離脱の原因にもなります。特にスマホ閲覧時に画面を覆うような広告やCTAを連発すると、ユーザーが操作しにくくストレスを感じやすいです。適切な距離感を保ち、コンテンツ本来の魅力をきちんと読んでもらえるレイアウトを意識しましょう。
また、ブログ記事から商品ページに移動した後もスムーズに購入手続きができるかどうかは非常に重要です。カートボタンや配送方法、決済画面に至るまでの導線を簡潔にまとめ、複数回クリックやページ移動を必要としないようにするなど、ECサイト全体のUXを見直してみてください。
ブログ読者の会員化・SNS誘導
初回訪問でいきなり購入に至らない場合も多いですが、ブログで興味を持ったユーザーを次のステップに誘導しておくことで、いずれ購買に結びつく可能性が高まります。そのために活用できる施策として、以下のような方法があります。
- メールマガジン登録のCTA: 「限定クーポン配布中」「新作情報をいち早くお届け」など特典を用意してメールアドレスを集め、後日改めて購入を促すことができます。
- SNSフォロー誘導: InstagramやTwitter(X)、YouTubeなどを運営している場合、記事末尾に「最新情報をSNSでもチェック」などフォローボタンを設置しておくと、ブログからSNSへユーザーを移せます。SNSで定期的に新商品やセール情報を発信し、購買タイミングを逃しにくくなる利点があります。
- LINE公式アカウント連携: LINEでクーポンを配布したり、チャット接客で疑問に答えたりする仕組みを作ると、ブログ読者と一対一に近いコミュニケーションが取れます。特に若年層向け商材では効果的です。
こうした会員化やSNS誘導は、ブログ記事そのものに購入ボタンを置くよりもハードルが低く、多くのユーザーに受け入れられやすい側面があります。将来的なリピート購入やファン化を狙うなら、“すぐ買わなくてもまずつながりを深める”ことを意識してみましょう。
参考事例:成功と失敗から学ぶ
実際に国内のECサイトがどのようにブログを活用して成果を上げているのか、あるいは失敗例から学べる点は何かを考察してみます。成功事例を見ると、必ずしも商品を前面に押し出しているわけではなく、有益な情報やエンターテイメント性を重視しながらブランドや商品の魅力を自然に伝えているケースが多いです。
「北欧、暮らしの道具店」の事例
家具やキッチン用品、雑貨などを取り扱う「北欧、暮らしの道具店」は、自社サイト内で雑誌のような読み物コンテンツを展開し、大きな成果を上げています。商品の紹介だけでなく、スタッフが実際に使用している様子や暮らしの中での取り入れ方を丁寧に発信。YouTubeやInstagramなど複数のSNSとも連動させ、コンテンツ自体がブランドの代名詞になっている好例です。
特にスタッフ試着レポートや実体験をベースにした記事は「サイズ感や使い勝手がイメージしやすい」と読者から高く評価されています。結果としてファンコミュニティが形成され、リピーターの獲得や口コミ拡散にもつながっています。
「KÓMERU(コメ兵)」の事例
中古ブランド品などを扱う大手リユース企業・コメ兵が運営するオウンドメディア「KÓMERU」は、開設1年で月間50万PVを達成。成功要因として挙げられるのは、ターゲットを明確に設定して女性向けファッションやジュエリーの記事に特化し、SEOとSNSを駆使した積極的な集客戦略を展開した点です。
社内リソースだけでなく外部のライターやメディアとの協業を行い、コンテンツの品質を保ちながら大量の記事を定期的に投入。さらに既存記事のリライトや拡散にも力を入れ、コンテンツ資産を最大限活用しているのが特徴的です。自社商品のPRばかりではなく、読者目線のトレンド情報や業界動向などを織り交ぜることで、飽きが来ない読み物を提供しているのも大きな強みといえます。
失敗例に学ぶ:品質と継続性
DeNAの医療系キュレーションサイトが、大量の低品質記事を量産して炎上した“WELQ問題”は、コンテンツマーケティングのリスクを象徴する事例として語り継がれています。ユーザーの健康にかかわる内容にもかかわらず、専門性や正確性を欠く記事が氾濫し、結果的にサイト閉鎖・大幅な信頼失墜につながりました。
ECブログでは健康や美容など、YMYL(Your Money or Your Life)領域に関わるテーマを扱う場合もあるかもしれません。その際は「正確な情報を伝える」「根拠や出典を示す」「専門家監修を受ける」など、より高い品質管理が求められます。また、「最初だけ頑張って更新し、すぐに止まってしまう」といったケースもよく見かけます。コンテンツマーケティングは中長期的な取り組みであり、継続的な記事投稿と既存記事のメンテナンスが欠かせません。
関連キーワードと効果的な活用
ECサイトのブログ運営には「ECブログ」「コンテンツマーケティング」「集客施策」といったキーワードが頻出しますが、それ以外にも多様なロングテールキーワードが存在します。それらを的確に活用するため、以下のアプローチを試してみてください。
サジェストキーワード・Q&Aキーワードの拾い上げ
「EC ブログ」という大枠のキーワードでは検索ボリュームが限定的であっても、「EC ブログ 運用 事例」「EC サイト ブログ メリット」「EC コンテンツマーケティング 失敗」など具体的な疑問形のサジェストは潜在的な検索ニーズを示しています。実際にサジェストやQ&Aサイト、SNS上で多く質問されていることを記事にすれば、“ヒットしやすい&読まれやすい”コンテンツを作りやすいです。
競合分析
同業他社がどんなブログ記事を書いているかリサーチし、そこに足りない情報や切り口があれば自社が先行して記事化するチャンスです。競合が強いキーワードに正面から挑むより、ニッチなテーマやロングテールワードをカバーするほうがスピード感をもって上位表示を狙いやすい場合があります。定期的なキーワード順位チェックや競合サイトの更新状況ウォッチを継続し、埋もれたチャンスを見逃さないようにしましょう。
検索ボリュームと難易度のバランス
月間検索ボリュームの大きいキーワードは一見魅力的ですが、競合サイトも狙っており上位を取るのが難しい場合が多いです。逆に検索ボリュームは中~低いが購入意欲の高いニッチキーワードを押さえておくと、コンバージョン率の高い見込み客が集まりやすくなります。数字で見るだけではなく、実際の検索結果の質や競合数を見て判断すると、効率的にSEO戦略を練ることができます。
継続的な改善と運用体制
ブログ運営は開始当初こそモチベーションが高いですが、数ヶ月経つと「ネタが尽きた」「更新する暇がない」といった壁にぶつかりがちです。ここを乗り越え、成果が出るまで粘り強く取り組むためのポイントを整理します。
運用体制とタスク管理
- 執筆担当・編集担当の明確化: ひとりが全てを担うのか、チームで分担するのか、あるいは外部ライターを活用するのかをあらかじめ決めておきましょう。クオリティチェック(誤字脱字、事実確認など)も重要です。
- コンテンツカレンダーの作成: イベントシーズンや新商品発売のタイミングに合わせて事前にどんな記事を書くかプランを立てると、記事ネタに困りにくくなります。月ごと・週ごとのスケジュールをガントチャート等で共有しておくとスムーズです。
- 定例ミーティングとKPI管理: 週1回や月1回など、定期的にアクセス分析や記事内容の振り返りを行いましょう。Google AnalyticsやSearch ConsoleでPV、滞在時間、CV率、検索クエリなどをモニタリングし、良かった点・悪かった点を共有します。KPIの例としては「ブログ全体のPV」「ECサイトへの遷移率」「実際の売上や問い合わせ数」などが考えられます。
既存記事のリライトとアップデート
一度公開した記事も放置せず、定期的に再チェックして内容を更新しましょう。特に数値データや市場動向などが古くなると、検索エンジンやユーザーに「信頼性が低い」とみなされるリスクがあります。最新の情報に差し替え、内部リンクを追加し、タイトルや見出しを微調整するだけでも検索順位が上がることがあります。
- リライトのタイミング: 公開後1~2ヶ月はある程度順位が安定するのを待ち、それでも伸び悩む場合は検索上位の記事と比較して足りない要素を補完。情報が古い記事や季節ネタは新年度やシーズンの前にリライトするなど計画的に行います。
- タイトル・見出しの再検討: 実際の検索クエリやユーザーのアクセス状況を見て、より刺さりそうな言葉を盛り込んだり、競合が使っていないキーワードを追加したりします。
他施策との連携
ブログ単独でも効果はありますが、SNSやメールマガジン、リスティング広告など他のマーケティング施策と組み合わせると相乗効果が高まります。例えば新記事を公開したら即座にSNSで告知し、最初のアクセスを呼び込むことで初期段階でエンゲージメントを高める。あるいは、リターゲティング広告でブログ訪問者に商品バナーを表示するなど、一度サイトに来たユーザーを再度呼び戻す仕組みを作ると良いでしょう。
さらに、実店舗を持っているならブログにクーポンを掲載して店舗来訪を促し、店舗での体験をブログでも紹介するなど、オンラインとオフラインを繋げる施策も可能です。ブログ記事は用途や展開先が幅広いため、一つのメディアとして柔軟に活かす意識を持つと運用の幅が広がります。
まとめ:ECブログがもたらす長期的な価値
ECサイトのブログは、単なる読み物ではなく、“集客”と“購買促進”を両立する強力なマーケティングツールです。商品ページだけでは伝えきれない情報を補完し、ユーザーに役立つ記事を提供することで、検索エンジン経由の新規訪問者を獲得できるのはもちろん、ブランド認知やファンづくりにも大きく貢献します。ユーザーが興味・関心を高めている状態で商品ページへ誘導できれば、購入率も上がりやすいでしょう。
しかし、コンテンツマーケティングは短期的な爆発力よりも、中長期的な資産形成を目的とする施策です。ブログ記事を10本や20本投稿したからといって、すぐにPVが急増したり売上が大きく伸びたりするわけではありません。定期的な投稿、既存記事のリライト、SEOやSNSとの連携など、地道な取り組みを継続することが不可欠です。
また、専門性と信頼性がますます重視される時代です。自社商品や業界知識を生かして「自分たちにしか書けない記事」を追求し、ユーザーからも検索エンジンからも高い評価を得ることを目指しましょう。大手事例のように、コンテンツがメディアとして確立すればブランドロイヤリティが高まり、リピーターや口コミによる拡散も期待できます。
最後に、ECサイト運営者が取り組むべきことは「売るためのブログ」ではなく「ユーザーに価値を届けるブログ」を作ることです。ユーザーが欲しい情報や知りたいノウハウに焦点を当て、そこから自然に商品購入へ流れるデザインを設計すれば、“押し売り感”を与えずに購買へ結びつけられます。ぜひ本記事を参考に、自社ECサイトのブログを長期的に育てる戦略を検討してみてください。地道な努力が積み重なるほど、必ず成果が現れるはずです。